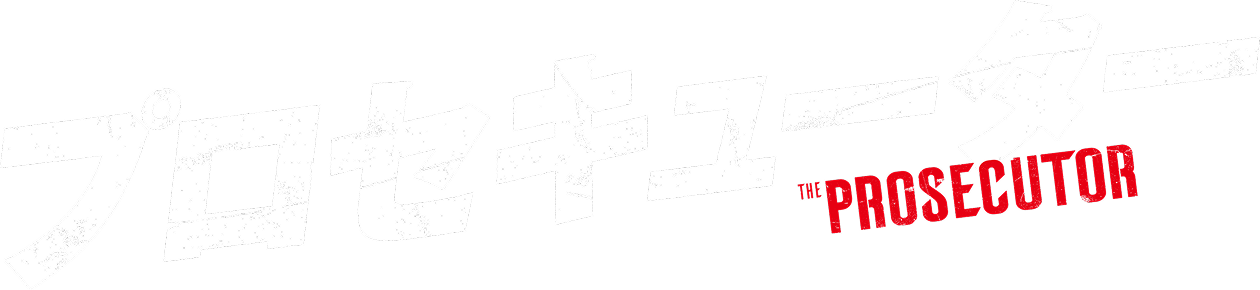Jason Cheung/張皓程(ジェイソン・チョウ)
香港法廷弁護士、ニューヨーク州弁護士
(日本での外国法事務弁護士未登録)
弁護士法人 淀屋橋・山上合同のフォーリンカウンセルです。国際商事仲裁およびクロスボーダー訴訟を専門とし、京都の同志社大学で国際法に関する非常勤講師も務めています。近年、日本の依頼者や弁護士から香港法に関するリーガルオピニオンを求められることが多く、特に日本とのクロスボーダー案件に携わっています。また、日本の裁判所を含む外国法域で使用される法律意見の提供にも従事しています。
本作をご覧になってどのくらい本格的な裁判になってますか?
これはなかなか難しい質問ですが、当然ながら現実の法廷手続と完全に一致しているわけではありません(そうであれば映画の時間内に収まらないでしょう)。ただし、映画の制作者は法廷の設定や法律事務所の描写などに一定の注意を払っているように感じました。香港の裁判制度の導入編として見るのには適しているかもしれませんが、一部は映画としての演出上、ドラマチックに脚色されている点があることも理解しておく必要があります。本作を通じて興味を持った方は、ぜひ実際に香港に行き、公開法廷の傍聴をしてみるとよいと思います。
ドニー・イェンのような検事はいないと思いますが、共感する部分はありますか?
現実の検事がドニー・イェンのように戦闘することはもちろんありません(笑)。ただ、香港では実際に警察官や税関職員などの法執行機関の出身者が、第二のキャリアとして弁護士や検事になることは珍しくありません。また、ドニー・イェン演じる検事やその同僚たちが法廷用のウィッグ(かつら)とガウンを着用している姿を見ると、まるで自分が再び香港の法廷にいるような懐かしさを感じました。
2016 年に香港で実際に起こった麻薬密売冤罪事件をモチーフにしている本作ですが、この事件についてご存知ですか?もしご存知でしたら、香港社会に衝撃を与えたこの事件について、当時、どういった社会現象になっていたか教えてください。
はい、とても有名な事件です。実際の事件名は HKSAR v Ma Ka Kin(馬家健)[2021] HKCA 1188 です。この事件は、香港の司法制度にとっての試練ともいうべきものでしたが、最終的には制度の枠内で解決され、香港における法の支配が依然として機能していることが証明されたとも言えます。特にこの事件は、香港大学の臨床法律教育チーム(Clinical Legal Education)が重要な役割を果たした点も注目されます(Jasonもロースクール時代別件でこのプログラムに参加していました)。この事件を通じて、香港にはまだ法の支配を守るために尽力している法律関係者たちが多く存在していることが示されたといってもよいでしょう。
本作のように、貧富の差からこういった事件は今でも起こっているのでしょうか?
なかなか一概には言えませんが、これは香港に限らず、日本を含め世界中どこでも見られる不幸な現象であると思います。
香港が中国へ返還されてから、法廷事情で変わったことはありますか?
香港終審法院の現任長官である張舉能(Andrew Cheung)長官が、香港司法機構の公式ウェブサイトで次のように述べています: 「香港特別行政区は、『基本法』に基づき独立した司法権を持ち、最終審判権も含まれます。司法機関は独立性、透明性、そして効果的な司法制度を維持し、法の支配および個人の権利と自由を保障しています。」
香港の裁判ではかつらはどんなことがあってもつけないといけないのでしょうか?
まず、香港の法曹制度はイギリス式を踏襲しており、弁護士は「ソリシター」と「バリスター(法廷弁護士)」の二つの職種に分かれています。1997年の返還以降も、「一国二制度」のもと、この制度は維持されています。ウィッグ(かつら)の着用は通常、バリスターと判事に限られ、すべての裁判で必要というわけではありません。現在のルールでは、家事裁判所や非公開審理を除き、裁判所レベルが地裁以上であれば、バリスターはウィッグと黒いガウンを着用するのが通例です。 また香港バリスター公会(バリスターの弁護士会)の案内からも以下のような説明があります: 「バリスターは訴訟や仲裁などの紛争解決における法廷弁論の専門家です。香港ではすべての裁判所においてバリスターは代理権を持っており、ソリシターは一定の試験を通過した者のみが高等裁判所で代理人として出廷することができます。」
なぜ、かつらをつけるのでしょうか?
この点については様々な議論がありますが、一般的にはコモン・ローの伝統を受け継ぐものとされ、制度的な厳粛さや法廷における格式を象徴するものとして理解されています。また、ウィッグの種類やスタイルによって、バリスターや裁判官の役職・経験年数の違いを示す意味もあるとされています。
日本とはここが違う!香港の法廷事情は?
一般論ですが、日本の裁判員裁判(裁判員は、事実認定だけではなく量刑を決めるのにも関与する)と香港の陪審制(陪審員は事実認定のみを担当し、量刑は裁判官が決める)は同じではないです。刑事裁判の証拠開示もだいぶ違います(日本では、検察官が持っている証拠を弁護人に開示するのは限定的。他方、香港では、全面的に証拠開示(disclosure)がされる)。
また、香港では判決文が法的先例(precedent)となるため、過去の裁判例は誰でも検索・閲覧することが可能です。たとえば今回モチーフとなった事件の判決も以下のリンクで公開されています:
https://legalref.judiciary.hk/lrs/common/ju/ju_frame.jsp?DIS=137806
日本でも、裁判例の検索システムはありますが、業者が提供するシステムを契約しないと、なかなか見ることは難しいです。